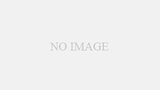教育実習では多くの実習生が先生という仕事の大変さを実感し、心が折れそうになることがあります。
そして教員になったときの将来を想像し、不安が大きくなってしまい教職への道を諦めてしまう人もいるでしょう。
私の経験上ですが、はじめから完璧を目指す必要はありません。そもそも完璧になんてできません。そしてそもそも学生に完璧を求めてもいません。
「もしかしたら学校の先生になるかもね」くらいにしか周りも捉えていません。
いうなれば職場体験のようなものです。
少し肩の力を抜いて「不真面目に真面目」でいることが大切だと思うのです。
今回は、私自身の経験を交えてお話しします。
教育実習は難しくて大変なのは当たり前
教育実習を難しく大変なのは当り前です。なぜなら「学校というプロの世界」で体験をしているわけだからです。
これまで小学校から高校までに接してきた先生方は全員、教育業界の経験を積んできているプロです。毎日生徒と向き合い授業を行い、教材研究をして、膨大な時間研修を行って来ているプロです。
自身が学生の側から見た先生は、一見、簡単そうなことをしているように思えるかもしれません。しかしそれはあくまでも表面上の姿です。
だからこそ教育実習というものがあり、さらには教員採用試験があり、そして初任者研修もあるのです。
その道を通ってきた先生たちでさえ、自己評価として満足いく授業はなかなかできないものです。
それがある意味「練習」や「体験」としてきている実習生が、上手く事をすすめられるはずがないのです。そしてそれは実習先も、実習の担当教員も、他の先生も全員がわかっていることです。
実習生が置かれる環境は特殊
私は小学校の教員免許を取得し、クラス担任として働いた経験があります。
教育には20年以上携わってきました。
そんな私から見ても、教育実習生がはじめて入るクラスで授業をうまく進めるのはとても難しいことです。
難しいというよりも「無理」といえます。
なぜなら1つの原因としては、生徒との関係性ができていないからです。生徒一人ひとりの性格や学力もわからず、生徒側も実習生との距離感がつかめない状態。そんな中で授業をうまく進めるのは、正直いって無理があります。
そもそもですが、自己評価として「今回の授業うまくいった」と思う先生は少ないと思います。それほど授業というのは実は難しく、100点満点の授業はベテランの先生でもなかなかできないものです。
「上手い授業」を目指しすぎない
実習生が考える「上手い授業」は、ベテランの先生から見れば未熟です。どんなにうまくて来たと思った授業だったとしても、ベテランから見ればまだまだでしょう。
私自身、教育実習はかなり苦労しました。前提として家庭教師経験もありましたし、塾では中学生の集団授業を円滑に行っていました。
その状態の中、教材研究も一生懸命しましたが、思ったような授業はできず、さらに思ったような生徒の反応は得られませんでした。
さらに予想外の生徒の反応にうまく対処することができませんでした。
結局できたのは大きな声で話すことくらいでした。
今思うと、そんなものだと思います。
教えることは勉強ができることとは違う
教員を目指す人の中には、自身が学生時代に勉強ができたという人は多いです。しかしだからこそ、実習現場では苦労することがあります。
あなたが理解できたとしても、生徒が理解できるかは話が違うためです。
逆に自身が勉強の理解度が高いからこそ、理解できない生徒のことを理解できない・・・という状況に陥ってしまうことがあります。
よくある先生を目指すきっかけ
先生を目指す理由は人それぞれです。
- 自分が勉強が得意だった
- 学生時代に良い先生に出会った
- 塾や家庭教師のアルバイトが楽しかった
- 学生時代のつらい経験を子どもたちには味わわせたくない
どれも立派な理由ですが、実際の教育現場は想像よりずっと複雑です。
学校と塾は全然違う
たとえば塾であれば、生徒は「勉強したい」という気持ちを持って来ています。
しかし学校ではそうとは限りません。勉強に対する意欲の割合でいったら学校の方が低くなりやすいです。
そこで求められるのは教える技術だけでなく、生徒の気持ちやクラスの雰囲気を読む力が求められると思います。
先生はプロフェッショナル
そもそも学校の先生は教育のプロです。何年、何十年も先生という仕事を毎日してきたプロなのです。
実習で見える現実
小中高で先生たちは身近な存在ですが、いざ教育実習で別の角度から先生を見ると、普段気づかなかったプロとしての一面が見えてきます。
そこでギャップを感じショックを受ける実習生もいます。
小中高の先生によい印象を持って学校の先生を目指している人は少なくないでしょう。
先生が生徒のために頑張っている姿、楽しそうに授業をしている姿。
それを見てあこがれを持つことでしょう。
しかし自習に来て、先生の、そして学校の裏の姿を見て、違和感を感じることがあるでしょう。
つまりそれは、今まで携わってきた先生たちが「プロ」であった証拠でもあるのです。先生たちが普段から生徒に大変さを見せないよう頑張っていた、そして頑張っている証拠なのです。
「不真面目に真面目」でちょうどいい
「不真面目に真面目」、「真面目に不真面目」。
どちらも矛盾しているようですが、これが大事だと思うのです。
肩の力を抜くことの大切さ
私は先生として働いているとき、「気楽にやろう。いつ辞めてもいいや。」と思ったときからうまくいくようになりました。
生徒のためによいと思うことを、楽しみながらするようにしたのです。
するとクラスの雰囲気も良くなり、保護者からも良い反応をもらえるようになりました。
自分が楽しんでいないと生徒も楽しみません。先生と生徒の距離もできてしまいます。
完璧を目指さない
私のやり方はある意味少数派なやり方かもしれません。堅物の先生からは注意されることもありましたが、先生全員に好かれる必要はないと思っています。
いい子ちゃんでいようとすると自分が苦しくなります。だから「不真面目に真面目」、つまり、適度に力を抜いて真剣に取り組むくらいが、実は一番ちょうどよいと思うのです。
自分が楽しくいることが一番大事
教育実習は完璧を目指す場ではありません。失敗して当たり前。むしろ失敗から学ぶことの方が多いです。
授業を上手にすることを目的としているわけではなく、少しの時間学校という職場を体験するだけのものなのです。よく中学生が行っている職場体験の少し長くなり深くなった版のようなものです。
肩の力を抜き、自分自身が楽しむ気持ちを忘れないでください。それが、教育の現場で一番大切なことだと私は思います。
ちなみに私の教育実習はかなり苦労しました。そして今思うと考えられない行動をしまくっていました。それでも単位は取れました。
だから安心してください。普通に過ごしていれば単位は取れますし、ほどほどに力を抜くくらいがちょうどよく、実習を楽しんでください。