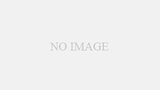2025年8月10日に、「臨時教員として塾講師や教員免許を持ち一般企業で働く人材を派遣する」ということを、文部科学省が検討しているという内容の記事を目にしました。
一見すると効率的な解決方法と受け取られるかもしれません。しかしここにはさらなる問題が出てくると考えています。
起こりえる問題
今回の検討が、実際に導入されることになったとしましょう。
少なからず効果はあると思います。しかし複数の問題があると考えます。
たとえば以下のような問題です。
- 勤務時間
- 勤務形態
- 報酬
- 生徒との関係
- 保護者の理解
- その他の問題
ここからは「塾講師」の立場としてお話ししたいと思います。
勤務時間
多くの塾は学校が終わった後の時間帯からはじまります。多くの場合14時、もしくは15時から教室が開きます。
塾の形態にもよりますが、生徒を呼び入れる1時間くらい前までには講師は教室にいるようにしています。
そして終わりは22時、もしくは23時くらいになります。
ということは、もし学校で働くとしても午前中の授業がメインとなることでしょう。
ただし塾の講師の仕事は教えるだけではありません。問題を作成したり集客をしたりしなければなりません。もちろん保護者対応もあります。
そう考えると意外と時間はないのです。
午前中に1コマ、もしくは2コマ程度であれば教えることはできるかもしれません。
ただしここでさらなる問題があります。たとえば数学の授業を担当していたとして、テストの問題は誰が作ることになるのでしょうか?採点は誰がするのでしょうか?これらを行うためにはさらに時間を要することになります。
結果として塾講師の業務に支障をきたしてしまう可能性があるのです。
勤務形態
臨時教員はあくまでも臨時教員です。
恐らく契約期間が定められることになるでしょう。つまり切られてしまうリスクがあるのです。
学校の先生の魅力の1つは安定していることです。基本的に解雇されることはありません。しかし講師や臨時教員にはそのリスクがあります。
そう考えると、臨時の方を大切にするのか、それとも本業の塾を大切にするのかというと、本業となってしまう可能性があります。
それでいうと、今回の臨時教員と同じような制度として「講師」という制度が昔からあります。しかしその講師でさえ現在は人手不足ということのようです。
講師が人手不足なのに、塾講師を対象とした臨時教員の制度を構築してもあまり効果はないと思います。なぜなら講師に魅力があるのなら、塾講師にはなっていないためです。
正規教諭と比べ講師の待遇は悪く、そういった面からも正社員としての塾講師の方が魅力と考える人は多いことでしょう。
報酬
教えることが好きであり、学校で働きたいと思う塾講師はいます。
しかしもし報酬が安いのであれば、勤めている塾で頑張ったほうがよいと考える人も少なくないでしょう。
生徒との関係
学校で授業をするということは、ただ授業をすればよいというわけではありません。生徒と人間としての関係作りが大切となります。
関係作りがどのようなものになるかによって、授業の質は大きく左右します。短い時間しか勤務できないと想定しているため、その中でどれだけの人間関係を構築できるのかは大きな疑問です。
保護者の理解
一昔前と比べ、保護者の学校に対する要求は大きなものとなっています。
見方からすると「片手間」で仕事をしている臨時教員をよく思わない保護者も出てくることでしょう。そういった人たちの対処を学校側が責任をもってしてくれるのであればわかりますが、それをどこまでしてくれるのかが疑問です。
その他の問題
上記した以外にも問題はいくつも考えられます。
まず現場の先生との連携がうまく取れるのか?ということです。1日のうち数時間しか勤務しないことを想定していますが、そういった場合、学校中の先生と連携がとりにくくなってしまいます。
また現場教員の理解も必要です。ある意味、学校での仕事の「素人」に対し、どれだけ協力体制を整えることができるのかという点です。学校には学校のルールがあり、それは塾の講師は知りえないことです。これを教えていく必要がありますし、理解してもらう必要もあります。
そこに対して大きな労力が必要となるでしょう。強要すれば離れていってしまいます。
また塾をメインの仕事としている場合、塾への営業をしてしまう臨時教員も出てくるかもしれません。
個人的な意見
個人的な見解をお話ししたいと思います。
私は小学校の教員免許を持っています。そして講師として3年間、小学校でクラス担任をしていました。これまでしてきた仕事の中で教員という仕事が一番良かったと思っています。
その立場からですが、今回の検討がもし実現したとしたら、少し複雑ではあります。
教員として働きたい思いはあるが
教員として働きたいという思いはあります。再び教員として教壇に立ちたいという思いはあります。しかし現在の仕事をしながら学校で働くことを想定すると、かなり体力勝負になることが予想されます。
働くからには責任も出てきます。生徒に対してもそうですが、その後ろにいる保護者に対してもです。
すると、かなり体力的にも精神的にも浪費されてしまうことは予想されます。結果としてメインの仕事に支障をきたしてしまう可能性も。
長く生徒と接するからよい授業ができる
経験上、長く生徒と接することができるからこそよい授業ができると考えています。
生徒一人ひとりの成績や能力、個性、バックグラウンドなど、さまざまなことを把握したうえで教えます。
たとえば1組ではこのように教える、2組ではこのように教える・・・など、クラス、そして生徒個人によって教え方を変化させます。
しかしそれをすることができません。とりあえずの授業になってしまうのです。
とりあえずの授業で生徒は満足するでしょうか?保護者は?
そしてほぼ高確率で、同僚である学校の先生から意見が飛んでくることでしょう。そのため周りの理解が必要となるのです。
目的が気に入らない
今回の主な目的は「人材確保を後押しし、教員の負担軽減につなげる考え」とのことです。
つまり主たるは学校の正規教諭ということになります。
塾講師はあくまでも「補助」に過ぎないのです。上から目線と捉えられてしまうと思います。
補助や代理でもそれ以上の魅力があれば可能かも
正規教諭の負担軽減のためだとわかっていたとしても、臨時教員として働く魅力があればよいかと思います。
- 学校で働くことが好きだから
- 待遇がよいから
- 正規教諭への道があるから
などです。
これらのいずれかが約束されるということであれば、かなりの人数が集まると思います。
それは逆にいうと、塾経営者側からしたら迷惑な話となりえます。そのため塾側としては講師の離職を防ぐため、待遇アップを迫られる可能性があるでしょう。
待遇アップをするということは、塾生の負担が大きくなる可能性があります。これはこれで別の問題が発生することでしょう。
ご都合主義が否めない
教員不足は近年の問題となっています。そのため文部科学省や各教育委員会は人材確保のために、さまざまな動きを見せています。
しかしどうしても「ご都合主義」に見えてしまうのです。
もっと門を広げればよい
例の1つとしては、教員採用試験の倍率は低くなっていますが、1倍を切っている都道府県は少ないです。つまり試験を受けて不合格になっている人はかなりの人数いる状態です。
そこで不合格にしておいて、人手不足であるといっているのは疑問があります。
教員採用試験は基本学力試験です。学力が多少足りないが先生としても資質のある人は数多くいます。さらにいうと、たとえば私は小学校の採用試験を受験しましたが、そこで出題される問題は学校で働いているときにほとんど役に立ちませんでした。
多少学力が足りなかったとしても、勉強すればある程度は何とかなります。何とかなりにくいのは教師としての資質の面です。
そのため、学力が多少足りない人材に関しては国として養成機関を用意すればよいかと思うのです。これによりこれまで学力でふるい落とされていた多くの人が教員としての道が開かれると思うのです。
まとめ
今回の文部科学省による検討は、実現すれば多少なりとも効果はあると思います。
ただそれにより、別の問題も出てくることが予想されます。
恐らくですが、あまり現場のことを知らない人たちの考えなのかとも思います。どれだけ現場教員、そして塾講師の話を聞いたのかはわかりませんが、もっと両者の意見をしっかり聞いて適切な判断をしてもらいたいと思います。