
新年度を向かえ新しいクラスになると「家庭訪問」が行われます。
家庭訪問には3つのタイプがあります。
- 担任が春、各家庭を訪問する
- 担任が夏休みに家庭訪問する。
- 家庭訪問はしないが、家の場所を確認し夏に保護者と面談する。
このいずれかの家庭訪問(家族面接)が行われているかと思います。
家庭訪問の4つの目的
家庭訪問にはもちろん目的があります。目的として考えられるのは以下の4つです。
- どのような家庭環境で育っているのか。
- 保護者の教育方針を知る。
- 保護者と担任の顔合わせ。
- 家の場所の把握。
どれも重要なことです。
他にも目的があるのかもしれませんが、私はこの4つを重視していました。
家庭訪問の各家庭訪問時間はものすごく短いのですが、その中でこれらのことを把握する必要があります。
大抵、1件あたり10分の滞在時間。その次の家までの移動時間5分。そのため、1時間で回れるのは4件程度。結果として、1日に10件前後を回ることになります。
ちなみに、回る順番は担任が決定します。あらかじめ、学校側から保護者に「○月○日は△地区」といった案内が配られるのですが、これはあくまで目安であり、担任が最終的には決定します。
最近では家庭訪問の主な目的は、家の場所の把握と言われています。子どもに何かあったら送り届けられるようにとのことです。そのため、家庭訪問をせずに各家庭の場所だけを確認しにいく方針の学校も増えてきました。
家庭訪問の裏事情
家庭訪問は先生方にとってかなりハードな仕事の一つです。
まず、道が分からない。
何年もその学校にいる先生であれば、ある程度地理的には詳しくなるのですが、初めて学校に赴任してきた先生は、全くの未開の地なのです。
地図片手に迷いながらの家庭訪問となります。さらに各家庭に行く時間が決まっているので、時間との勝負になります。
「遅れちゃいけない」
そう思えば思うほど焦ってしまい、車がぶつかりそうになったとか、スッてしまったとか結構話を聞きます。ベテランの先生になると、自転車で回る手段を取っている方もいました。ちなみに私は一度車を擦ってしまいました・・・。
また、ケーキや飲み物を出してくれる家庭が沢山あります。事前に「何も出さなくても良いです」と学校側からお伝えするのですが、皆さん気を使ってくれて色々出してくれます。
手をつけないのも失礼だと思い、私の場合は出されたものはいただく主義なのですが、家庭訪問後半ともなるとお腹がパンパンになってしまいます。
一番ありがたかったのは、「缶コーヒー」や「ペットボトル」を出してくれた家庭でした。
持ち運びができ、好きなときに飲むことができるためです。
ちょっとしたテクニック?子どもに伝えておく
「家庭訪問では何も出さなくても良いです」と学校側からのプリントが家庭に配布されるわけですが、それでも何かしら出してくれる保護者もいます。
ある学年主任に聞きました。
「家庭訪問の時、お菓子や飲み物を出していただけることがあるのですが、主任はどうします?」
すると
「せっかく出してもらってるんだから当然いただく。見てみろ。俺の家庭訪問の計画表を。ここに休憩時間があるだろ?いろいろな家で飲み物をご馳走になるからトイレ休憩のための休憩時間だ。」
なんとたくましい・・・。
ちなみに何年か家庭訪問を経験していると、こちら側としても多少知恵がついてきます。
子どもたちにこのように伝えます。
「今度家庭訪問でみんなの家に行きます。色々出してくれるのはありがたいが無理はしなくてもいい。もし、もしだ。もし何か飲み物を出してくれるのであれば、持ち運びができる缶コーヒーやペットボトルタイプが最高。」
この言葉を投げかけてからの家庭訪問。どの家に行っても缶コーヒーかペットボトルが出てきました・・・。終わるころには大量の飲み物が。



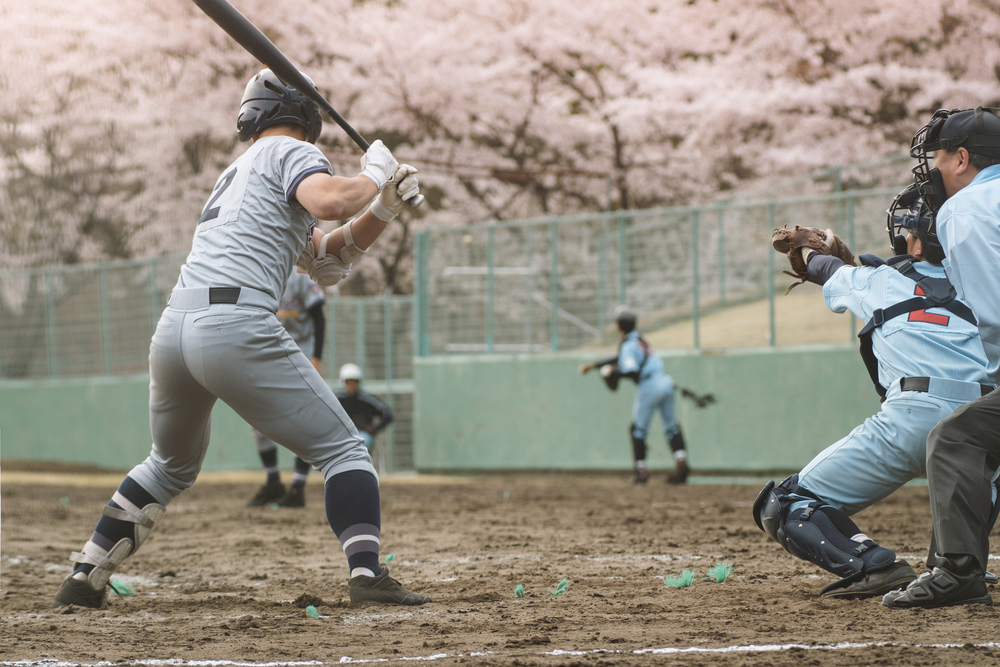
コメント